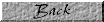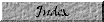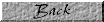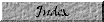|
親指で先の窪みを、人差し指で括れを、幾度も撫で擦りあげて、さらに蜜を溢れさせる。中指と薬指で幹を握り扱きあげ、さらに嬌声を誘う。堪えられないほどの快楽に身を捩りながらも、緩く首を振り間断なく嬌声を零し、熱い身体に擦り寄っていった。甘い刺激に腰を蠢かせながら、精悍な貌へ寄せた唇で啄ばむように口付ける。
首へ腕を回し身体をぴったりと寄り添わせ、温もりを分けながら抱擁を繰り返して唇で触れる。やはり、どこか急いたような仕草。
「あ……っは、ぁ…」
媚肉を穿たれ昂ぶりを弄られて、少しづつ声が高くなっていく。とうとう唇が離れ、甘い声が断続的に響き始めた。それにつられるようにして、腰までがゆらゆらと蠢く。それに応えるように時折細腰を突き上げ、手の平全体で昂ぶりを追いつめていった。
「や…ゃ…も、ぃ……っ」
前後を同時に弄られて、余裕がどんどん無くなっていく。くちくちと湿った音が昂ぶりから聞こえてくる。そのぬめりを借りてさらに煽るように擦りあげた。ややするとあっけなく昇りつめ、濡れた声で開放をねだり始める。
その声を無視すると、弾けそうになった瞬間に昂ぶりの根元をきゅうっと締め付けてやり、滾る熱を堰き止める。
「まだだ」
短く言い捨てると、蕾を穿ち前を握りこんだまま、ぴたりと動きを止めてしまう。身体の中でとぐろを巻く深い慾。焦れた神経が快楽に蝕まれていく。
ルヴァは目の前のつれない身体に縋りつき、彼の名を幾度も呼んだ。
行き場所をなくした熱は神経を侵してさらに深い悦を身体に与えた。達くことができないまま放置され、熱が落ち着いたと判るとまた弄られて、焼ききれるような快楽に晒される。
「…ゃ……や、ぁ………」
涙を零しながらかぶりを振る。許しを乞うような瞳が揺れ、ただ、唇からは悦に染まった声だけが聞こえた。
「どう、したいんだ」
望みを口にするまで容赦なく攻めたてる氷色の瞳。媚肉から受けとる悦は確かに精悍な身体へと流れ込み、また、ルヴァの体内でその質量を増した。時折思い出したかのように不意に突き上げられる身体は、その都度びくびくと快楽故の反応を返す。
痺れるような快楽に浸された身体。
「…ぉ…ね、が……っ…ぃ…」
戦慄く肢体。
「も……ぅ…っ…」
震える腕を差し伸ばして身体を寄せ、涙を流しながら唇で唇に触れる。
「…お願い……で…す…」
幾度も幾度も触れては離れ、離れては触れて吐息を交わしていく。
「もう………っ、め……も……っ」
堰きとめたまま、蜜を零してしとどに濡れそぼった昂ぶりを弾く。
「や、あ、あっっ」
「ちゃんと言わなきゃ、判らない」
耳に心地よい、嬌声。こくりと息を呑み、再び唇が近付く。
「……っふ……ん、ん…っ」
雑じる吐息、絡み付く舌、触れ合う唇、全てが甘い。
「っか…せ…………達…か、せ…て……っだ、さ……ぃ…っっ」
望みの通り、昂ぶりの根元を拘束し熱を堰き止めていた指を外し、悦を欲しがる腰を強く抱き寄せた。
気を失ってしまった身体から自身をゆっくりと引き摺り出して、膝の上で抱きしめる。抜けきる瞬間、ひくりと戦慄く肢体にそっと口付けた。
汗で額に張り付いた髪を掻き揚げてやり、未だ桜色に染まる頬にもひとつ口付けを落とす。好い香りのする身体を、きつく抱きしめた。
傍にあったタオルで汗や汚れを拭い取り、ブランケットに包んだルヴァをそうっと横たえる。自分も彼の隣に寝転がって、寝室の床から引き摺り戻した上掛けを被った。柔らかい蒼の髪を撫で、頭を抱えるようにして腕の中に抱き込む。額にも口付けると、髪が頬を擽り、また好い香りが流れる。す、と寝入っている筈の彼の腕が動いて、自分を抱く逞しい腕を掴み、ふわりと微笑んだ。
その笑顔に、胸が締め付けられる。
腕枕をしながら細い肩を抱き込み、もう片方で柔らかい髪を梳く。
「ルヴァ……」
室内を仄かに照らす間接照明の光が、やすらかな吐息を零す彼の人の輪郭を浮かび上がらせる。氷色の瞳が細められ、き、と唇を噛み締める。ほんの少し身体を起こして、そっと柔らかい唇に口付けた。
「俺が、傍に居る……だから…」
続く言葉は、呟くような声になり、夜の闇の中へ静かに融けていった。
Fin
|