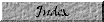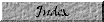|
朝。いつもの時間。
そろそろ起床の時刻だろうと年若い女官が飲み物と着替えを用意して向かうと、部屋の主は既に起きており、涼しい風の舞い込む窓辺に置かれた長椅子に腰をかけて静かに読書をしていた。些か慌てて扉を閉め、時間に遅れてしまったかと時計へ視線を走らせれば、いつもならまだ主の姿はベッドの中にある時刻だった。
いずれにしても遅くなってしまったことに変わりはない。ベッドの上に着替えを置き、遅くなってしまい済みません、と窺うように長椅子へ近付くと、頁へ落とされていた青鈍の視線がゆるりと持ち上げられた。
「ああ、すみませんねぇ。其処へ置いていただけますか?」
ふわりと落とされる穏やかな声。人当たりの良さでは聖地随一と言われる程、その人柄の良さは誰もが認めている、地の守護聖ならではの微笑みと共に落とされた言葉に、恐縮してしまっていた女官の表情が微かに和らいだ。
申し訳ありませんでした…、と頭を下げる彼女に視線を向け、気にしないでくださいね、と首を傾けて微笑む。その情景は、常日頃と変わらぬもので。ひとつ違うのは、朝がそこそこ苦手だった彼が、起こしに向かった女官よりも早く起きていたこと。
カップをテーブルへ置いてもう一度頭を下げ、女官が部屋を退出する。閉めようとした扉の向こうで、いつもなら直ぐには手をつけないカップへと手を伸ばし、くい、と半分ほど一息に飲んでしまう彼の姿が目に映る。再三の違和感に小さく首を傾げながら、たまにはこういう日もあるのだろう、と、女官はその場を後にした。
いつもなら、そろそろ聖殿へ出かける時分。
時計を見上げ、聖殿へ上がる時の正装を用意して主の私室へ行こうとしたその肩を、不意に留められた。疑問を纏う貌を振り向かせた先には、古参の女官が立っていた。
「今日は、お出かけにならないから。悪いのだけれど、しまってきてくれる?」
腕の中の服を示しながら微笑む。具合でも悪くなければ聖殿へ上がらないことなど全くと言っていいほどにないはずで。見落としてしまったかと些か慌て首を傾げながら、朝お姿を拝見したときは、どこも調子悪そうには見えませんでしたが、と訊ねた。浮かんでいる疑問の意味を得たとばかりに軽く頷き、子と母程にも年の違う彼女が、女官の髪をゆるりと撫でる。
「違うの。お加減が悪い訳ではないから…心配しなくても、大丈夫よ」
気付かずに失敗をしでかしたかとうろたえる年若い女官の髪を宥めるように数度撫で、笑みを深める。そうですか…、と少し表情を沈ませて俯いた彼女の肩越し、館の入口でベルが鳴った。古参の女房が柱の時計を見上げ、ああ、と言葉を零すと、そのまま玄関へ向かおうとする。
「それ、片付けてから、私室の方へ来てくれるかしら?」
扉のところで振り返り訊ねる彼女に、はい、と大きく頷いて見せる。笑んだままその様子にこくりと頷きを返し、古参の女官は扉の向こうへと姿を消した。
失礼します、と会釈と共に扉を開け、貌を上げた瞬間。光景に目を奪われる。
「ああ、丁度よかったわ。着付けを手伝って」
貌を上げ視線を扉の方へと向けた古参の声に、漸く我に返った。
部屋に溢れていたのは、いつになく華やかな色彩の服や布達だった。一般的には大人しい色調ということになるのだろう、けれどこの舘の主にしてみればそれは色とりどりと言って差し支えないもので。それらはどうやら主の故郷の民族衣装らしく、しきりと懐かしがっている様子が妙に幼く見えた。
言われるまま近付き、示される箇所を押さえ、紐を巻き、着付けていく。
「手触りも懐かしいです…」
ほうっと溜息混じりに零れた声は、何処か郷愁に満ちていて。表情を見てみたい衝動に駆られる自分を宥めながら、暫くして着付けを終える。
「…よく、お似合いですわ」
古参の賛辞に、照れたような笑みが零れる。
流れるような曲線で身体を包み込む艶やかな肩布、織込み模様も鮮やかな上質の腰巻。男性に対して『綺麗』という形容は如何かと思うけれど、ゆるりと微笑み身体を捻るようにして後ろの裾を見遣る主の姿はいつになく綺麗としか言い様がなく。胸のところで手を組み微笑んで主を見る彼女の隣に並び、倣うように視線を向けた瞬間、再び目を奪われる。
何処か凛々しさを漂わせ、かつたおやかないつもの風情を残し、照れたように微笑む姿は今まで目にしたことの無いもので。ありがとう、と落とされた言葉に深々と頭を下げる古参の隣で惚けたように見詰めてしまっていた女官は、ぐ、と頭を下げさせられて漸く我に返る。
「急な仕立てでしたが…間に合ってようございました」
頭を上げながら隣の古参がそう返し、それでは失礼致します、と部屋を退出する。引き摺られるように退出した女官は、部屋の直ぐ外でほうっと溜息をついた。
常ならぬ事柄が重なる今日。何かあるんですか?と古参に問う。ふふ、と意味ありげな微笑が返された。
「今日は、一年に一度の大事な日、なのよ」
意味が取れずに首を傾げる女官に、古参は前へと視線を流しながら、もう一度ゆるりと微笑んだ。
日が高く上がりかけた頃。玄関の呼び鈴が鳴り、料理に取り掛かっていた者に厨房を任せると、古参がひとり玄関へ向かった。
隣で鍋を掻き混ぜる少し年上先輩格の女官を見上げ、誰かな、と首を傾げると、手元はそのままに、上肢を僅かに屈ませて小さい耳打ちが落とされる。
「懇意にされていらっしゃる方、らしいわよ」
ふうん、と軽く頷く女官の後ろで、オーブンから焼きたてのスポンジケーキを取り出してきた女官が小さな声を掛ける。
「私が聞いた限りでは、とても素敵な方なんですって」
寄るとお喋りが始まるのはどこでも同じなのだろうか。そのまま走り出そうとするお喋りを、年長の女官が窘める。
「おしゃべりはほどほどにして、さ、早く仕上げてしまいましょう」
スポンジケーキを持った女官を手招きし、甘さを押さえた生クリームやフルーツの用意を指示する。いつもは用意されないそれに怪訝な表情を浮かべると、戸棚から皿を取り出してきた女官がそっと耳打ちする。
「今日は、御館様の御誕生日なんですって」
得心のいった貌で頷き、ふと首を傾げる。そんな日に訪ねてこられる方って、一体…、と思わず零した言葉に、気になるわね、と興味津々といった声が返される。
鍋から少しスープを掬い味見をする女官の隣で、付け合せ用の野菜の下拵えをしながら。着付けをしたときのお顔、何処かとても嬉しそうだったし……大切な方なのかしら、と呟く。そうかも、と、鍋を掻き混ぜていた女官が頷きながら呟いた。
料理が出来上がり盛り付けが済むと、それを見計らったように古参の女官が厨房へ戻ってきた。
「御食事を運ぶから……貴女と…貴女、手伝ってくれるかしら?」
年長の女官へまず注がれた視線が、次の瞬間年若い女官へ注がれて、思わず息を呑む。朝や昼の用意は経験があったが、晩餐は初めてのこと。常から年上の女官の手で行われていた為、突然の指名に彼女自身驚き、近くに居た同僚から羨望の眼差しが注がれた。
古参の言葉に応えるように、先に指名された先輩格の女官が、奥からワゴンを引いてくる。
「…貴女、スープを器に入れて持ってきて?」
ワゴンの調整を終えて貌を上げた女官に声を掛けられ、漸く我に返る。はい、と慌てて返事をしてスープ鍋へ向かう年若い女官へ、古参が微笑ましげな視線を寄せる。
火加減を確かめながら掻き混ぜるその隣へ同僚が器を運んできた。ありがとう、と薄く笑みを返して僅かに視線を振る。零さないよう注意しながら注ぎ分けていく様子を見ながら、よかったね…頑張って、と、同僚の声が零された。
古参の先導の下、年若い女官が押すワゴンの隣には先輩格の女官がつき、主の私室へと向かう。高まる緊張に表情が強張る後輩に、ワゴンに手を添えながら微笑みかける。
「夜は初めてだったわね……大丈夫よ、そんなに緊張しなくても」
優しい声音に微かに表情を緩め、はい、と頷いて返す。廊下の角をゆっくりと曲がり、私室の扉が目に入った。
扉の前でワゴンを止め、古参が最後の確認をする。細かい細工が施された扉の向こうから洩れ聞こえてくるのは、楽しそうな笑い声。こんなに楽しげな声を聞くのも初めてで、また緊張してしまいそうになるその肩を、ぽん、と叩かれて苦笑する。
「それじゃ、入るわよ」
確認を終えた古参が身体を起こし、ふたりへ微笑みかける。同時にこくりと頷き返す後輩に笑みを湛えて頷き返し扉に向かうと、軽くノックをした。
「御食事をお持ちいたしました」
ああ、済みませんねぇ、と柔らかな主の声が中から返ってくる。失礼します、と押し開かれる扉の向こうから、楽しげに笑う主と、歓談しているのだろう来客の声が耳に届く。緊張とは少し趣の違う高揚を微かに感じながら、開かれた扉の内側へとワゴンを押して入っていく。
そうして、近しい者に囲まれての誕生日を祝う晩餐が、静かに始められた。
<FIN>
|