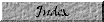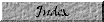初めての出会いから数年、互いの想いを確かめ合ってから数ヶ月。いままでの自分だったなら、『君の素肌を今夜俺だけのものにしたい』なんて気障な台詞をいいだけ並べて、甘い夜を存分に謳歌していても不思議じゃないくらいの時間が経っている。いままでの自分だったなら、褥を共にすることも、朝日をふたりで見ることも、疾うに何度も経験していていい筈だった。
「本当か…?」
一瞬自分の耳を疑う。抱きついてきた身体をどうしたらいいのか思いつかぬまま問うと、頭の横に垂らしているターバンの裾を揺らしてルヴァがこくりと頷いた。
「本当に―――、…いいのか?」
「え…あの……本当は一寸、怖いですけれど…」
つい念を押してしまった俺の言葉に、不安げな声がぽつりと零れた。ここで引かれてしまっては今までの苦労が水の泡だ、と少し焦りを覚える。どう言い包めたらいい、と過去の記憶を手繰り寄せようとした俺の目の前で、けれどルヴァは照れたように微笑った。
「でも、オスカー、…貴方とだったら……いい、と思うんです」
言葉と共に白い手が差し伸ばされた。反射的に手を差し伸べて、自分よりも少しだけ細い肩を抱き締めた。
浮薄な恋を求め一夜限りの逢瀬を今まで幾度も重ねてきたことは、今更否定しない。愛を語らうべき相手を見つけたなら速やかにかつ情熱的に然るべき関係へ発展させる、というのが身上だった俺が、しかし彼を目の前にしてしまうと、まるで初めて恋をした男のようになってしまう。いつになく慎重に、そして幾分か臆病になっている。口付けくらいは交わしているものの、未だにそこから先へは踏み込んでいない。いやむしろ、踏み込ませて貰えなかった、というべきだろうか。
今までのように雰囲気を大事に婉曲的な表現を駆使するというやり方は、そういうことに疎いルヴァには全く通用しなかった。こちらが誘っているつもりでも、極度に天然な切り返しで肩透かしを喰らってしまう。
いつだったか、夜に私邸へ遊びに行った時のことだった。テラスへ誘い、持参したワインをあけてグラスを傾けていると、暫くして幾分か酔ったルヴァが俺の肩口へ凭れかかってきた。
『あー、…なんだか少し酔ってしまったようですよー』
『大丈夫か?…随分顔が赤いが』
肩口から見上げてくる目は、酔いの所為で幾らか潤んでいた。随分とそそられる表情に誘われて肩へと手を伸ばしてみると、嫌がる素振りも慌てる素振りも見せず、むしろルヴァの方から俺の肩へと顔を寄せてきた。
赤く染まり艶が増して見える目許が間近に見え、心拍数が上がる。この流れならもしかすると今夜こそは、と緩く抱き寄せ、頬へ手をかけて上向かせようとした。
『―――あ』
『…え?』
上向いたルヴァは、俺の顔ではなくその遥か後方を見ながら、なんとも言えない声を上げた。そして事情が呑み込めず訝しげな顔をする俺を他所に、がたりと立ち上がりテラスの縁へと歩き出て空を指さした。
『あそこに、…オスカー、ほら、流れ星です! …ああ、すごいですよ、こんなにたくさん―――』
仄かに赤く染まっている顔に満面の笑みを浮かべ、目をきらきらと輝かせて、突如現れた流星群にルヴァは感嘆の声を上げた。一連の行動に不自然なところはない。これで素なのだから罪作りもいいところだ。
浮いた手を仕方なく収め、苦笑混じりの溜息をついて立ち上がる。手摺に身体を寄せて星を見上げる彼の後ろに立ち、緩く抱くようにして腕を手摺へと伸ばして一緒に見上げた。
『珍しいな、本当に』
『ええ、本当に……貴方と一緒に見ることが出来て、よかった』
肩越しに振り返ったルヴァはそういって緩く微笑い、俺の肩に頭を軽く預けてまた夜空を見上げた。
『ああ…そうだな』
心地好い重みに目を伏せ、ターバンに包まれた頭へ頬を寄せる。
そうしてその夜は、ワインがなくなるまでふたりで夜空を眺めて終わった。
過去の経験からすれば、こういうことが続いた相手には早々に見切りをつけて『知人』に留まることにするのだが、彼に関して言えばどうしても踏み切れない。肩透かしを喰らい脱力したりはもちろんするのだが、その後にフォローめいた言動が続くから余計に思い切れない。時々は全て計算ずくではないかと思うほどの徹底振りに、今では慣らされてしまっている感すらある。
結局は惚れた方の負けなのだ。そういった天然なところを含めて彼を愛おしいと思うのだから。
|