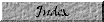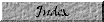|
さらりとルヴァはターバンをはずした。
眠る前のひととき、夜着を身につけ、鏡の前に立つ。
そっと、常に形の良い頭を覆っている柔らかな白い布を巻き取る。
蒼い髪が現れる。
少し、困ったように、ルヴァは鏡の中の自分に笑いかけた。
泣きそうな、情けない顔だと思いながら、ターバンをはずした自分の姿を見る。
見慣れたようで、見慣れない姿だ。
ルヴァがターバンをはずすのは入浴と睡眠のときくらいで、昼間は常にターバンをつけているから、それがない自分の姿はルヴァ自身もあまり見たことがない。
あるべきところにあるものがないような、軽い違和感が襲った。
ルヴァは鏡の中の自分を見つめ、そっと目を細めた。
ふわり、と軽い浮遊感が襲う。
髪を、そっと触った。
こめかみにからそっと指を差し込み、そのまま梳き上げる。
じわり、と半身に軽い寒気が走る。
はふ、と小さな吐息が漏れ、慌てて唇を噛んだ。
自らの手で、ゆっくりと髪を梳きながら、次第に吐息が荒くなる。左手で、喉から胸へ指を滑らせた。
鏡の中の自分が喘ぐ。
薄く目を開け、肩を大きく上下する自分の姿を見つめながら、ルヴァは乾いた唇を舐めた。
こうして、抱かれたのだ。
こんな鏡の前で、あの人に。
するり、と薄い夜着を肩からすべり落とす。
薄い肩が現われた。
撫で肩の細い肩。肉の薄い肌がひどく白くて、貧弱な体だと、ルヴァはいつも思っていた。
頬をなぞった右手をそのまま下ろし、肩を抱いた。
でも、きれいだといわれた…
こんな風に、抱きしめられて、耳に囁かれた言葉がよみがえる。
薄い色をした乳首をそっと指でなぞる。
ビクリとからだが震えた。
その、全てが見える。
薄く口をあけて、息を吸う。
目に涙が浮かんで、とけたようになっているのがわかる。
口元にこぼれる息が熱い。
喉の奥からかすかな声を絞って、ルヴァは性急に指を下肢に進めた。
夜着の中に滑り込ませる。手が入り込んだ分だけ布地が盛り上がるのが鏡越しにも良く見えた。小さく、耐え切れない声を上げながら、ルヴァは鏡の中の自分を凝視し、指を蠢かせる。
薄い布地を揺すって、ルヴァのもっとも敏感な部分で蠢くものがある。
残った指で、そっと布地をよけた。
いやらしくとどろく指と、それに合わせて頭を振る己の欲望。
あ………あぁ…………
ルヴァは一瞬目を閉じる。
だが、止められない指の動きに、そろそろと目を開けた。
『 よく見るんだ 』
優しく残酷に囁かれた声が、聞こえる。
目を逸らそうとする自分をいつもそうして鏡の中に引き寄せた声。
『 ほら…オレにされて悦んでる…嬉しいよ、ルヴァ 』
淫蕩な見るに耐えない恥かしい自分の姿を見せつけられ、それでもあの人は誰より優しかった。
自ら腰を擦りつけ、欲望を煽るしぐさを指摘され、泣きながら、それでも鏡の中の自分とあの人を凝視した。
ルヴァの指の動きが激しくなる。
くち、と軽い水音が響くと、嬉しそうに目を細めた。
髪に触れる。
襟足から、指を忍ばせて、普段決して人に晒されない後頭部を梳き上げる。
いつも後ろから抱かれたから、いつもここに、あの人の熱い息が触れていた。
あっ…………んん………んぅっ………
喘ぎながらルヴァの目に涙がこぼれる。
快楽と、寒さと。
背中に触れない、かの人の熱を求めて、無意識に身を捩る。
目の前には、独り、欲望を擦り上げ、身を捩る男の姿が映っている。
たった、独り………
…………………………………っっ! …………………
声もなく、細く息を吸い込んだ。
ぱたぱたと、目の前の硝子に白い液体が飛ぶ。
目を細め、それでも目を逸らさなかった。
『 見ていてくれ… 』
と、教えられたから。
初めて抱かれたときから、いつもこうして鏡の前で、鏡の中の自分を欲望で汚してきた。
こうして、終わるものだから。
くたり、と欲望を支えていた手が抜ける。
がくりと腰を落とし、ルヴァは、今しがた汚した鏡へ、膝でずるように向かう。
鏡の前で手をついた。
目の前に、己の吐き出した、白い残滓が残る。
吸い寄せられるようにそれを見つめ、ルヴァはまた辛そうに目を閉じた。
顔をそむける。
震える息を幾度もついた。
白い頬を涙が伝う。
泣きながら、ルヴァは意を決したように再度それに向き合う。
喉の奥で嗚咽を洩らしながら、そっと顔を近づけた。
震える舌を伸ばす。
まだ温かいそれを、そっと、丁寧に舌で掬い取る。
涙が途切れなく流れる。
けれど、止めなかった。
全て、己で汚した全てを消してしまうまで、丁寧に、丁寧に舐め取った。
こくり、こくりと、細い喉がそれを飲み下して動く。
ルヴァの喘ぎと泣き声。
独りの部屋に響く声の残響を、ルヴァはどこかで他人事のように聞いていた。
『 よくできたな 』
そう言って、抱きしめてくれるあたたかな腕。
カティス…
全てを舐め尽くして、ルヴァは転がるように、ソファに身を沈めた。
手元のクッションを引き寄せて、きつく抱きしめる。
ぶるぶると肩が震えた。
カティス
暖かな、優しい腕が、今はない。
子供のように手足を縮めて丸くなりながら、ルヴァは細く、かの人の名前を呼びつづけた。
あなたに…教えられた通りにしたのに…
暖かな、あなたの腕だけがない。
ルヴァはきつく目を閉じ、寒そうに体を丸めた―――
了
|