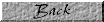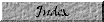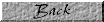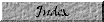これから暫くの間に取るべき処置、惑星の変動を抑え安定へと導く方策について相互に確認を終えた後、会議は終了となった。
幾分か張り詰めていた場の雰囲気が緩み、歳若い守護聖達が真っ先に外へと飛び出していく。久しぶりに私邸へと帰宅できることが嬉しいのだろう。
リュミエールは手許の資料を膝の上で軽く揃えて立ち上がり、周囲を見回した。少し離れたところでルヴァが、資料を片手にロザリアと話している。一週間ぶりに見る彼の人は、ほんの一週間離れていただけなのにどこか懐かしく、そして少しやつれたように見えた。
書庫へ調べ物に行ってきます、と言い残したまま半日経っても戻ってこない、下手をすれば寝食を忘れ書庫に丸一日籠もりきりになる。そんな話は、ことルヴァに関して云うならば枚挙に暇がない。地の守護聖付きの執事が心配して朝食を届けに行く姿も、数え切れないほど目にしている。
今回の調査・分析の際も、何よりも大きい知識欲が故にまた無理をしたのではないだろうか。そんなことを考えている間に話は終わったらしい。先刻まで話をしていたふたりが軽く会釈を交わしていた。
「では、失礼致します。―――今晩はちゃんと、私邸の方へお戻り下さいませね?」
語尾に少しだけ砕けた雰囲気を滲ませたロザリアの台詞に、ルヴァが小さく笑って応える。
「ええ、『今晩は』しっかりと休みます」
「そうしてくださいませ。…でないとわたくし、陛下に怒られてしまいますわ」
「あー、…それでは本当にしっかり休まないといけませんねぇ」
お願い致します、と微笑んだロザリアは、判りました、と頷くルヴァに一礼し、部屋を出ていった。
扉が閉まる音を聞きながら、リュミエールはルヴァの許へと足を向けた。彼が私邸へ帰ってしまう前に、ほんの少しだけでも話がしたかった。己だけに向けられた声が聴きたかった。しかし。
「ルヴァ、少しいいか」
己に先んじてルヴァへと声を掛けられてしまい、リュミエールは中途半端なところで立ち止まる。
声の主は、ロザリアとルヴァの会話を間近で聴いていたジュリアスだった。
「疲れているところ済まぬが、現地の様子について聴かせて貰えないだろうか。…力を送る際の参考にしたい」
「ええ、構いませんよ。どういったことをお話すればいいですかねぇ」
ふたりの『話』は、長くなる気がした。
「資料を見ながら話をしたい。―――私の執務室へ来てくれるか」
やはり、『話』は長くなるらしい。守護聖としての責務、それを果たすための用件であれば、『仕方無い』と思うしかなかった。
また明日がある、と思いながら踵を返し、扉へ向かう。取っ手に手を掛けたところで、己が名を呼ぶルヴァの声が聞こえた。
「リュミエール、済みませんね、待っていてくれたのですか? 後で私邸へ伺いましょうか?」
優しい声がじんわりと沁みていく。取っ手へ掛けた手を放して向き直り、緩くかぶりを振ってみせた。
「ありがとうございます、ルヴァ様。ですが、ジュリアス様とのお話が終わりましたら今日は私邸へお帰りになって、ゆっくりお休みください。私の方は、明日改めてお伺い致します」
「そう…ですか? それならば、いいのですが」
いつの間にか、部屋に居るのは三人だけになっていた。
「はい、…では、先に失礼致します」
「ああ、リュミエールも私邸へ戻るのは久しぶりだろう、ゆっくり休んでくれ」
「明日、執務室で待っていますね」
軽く会釈を返し、扉を繰って廊下へと出た。
ゆっくりと扉を閉めてからくるりと身体を返し、背を預けて深く息を吐く。
「…どうした、溜息などついて」
「! ―――クラヴィス、さま…いらしたのですか」
不意に掛けられた声に驚き横を見遣ると、扉の直ぐ脇にクラヴィスが佇んでいた。
「あれがいつまでも居るから、先に出ていた。―――リュミエール、…楽を所望したい」
気配を消すのが得意なのか、存在を気取らせずにいられる質なのか。リュミエールはクラヴィスのそういう所によく驚かされる。上がりかけた心拍数を静めるように、浅く息をつく。
そして、いつもなら苦笑してしまう『あれ』という呼び方を、何故か好ましく感じている自分に気付いた。今この時だからこそ、なのだろう、と現金な己を思いながら、和らいだ表情を載せて緩く頷いた。
「はい、喜んで。…場所は、クラヴィス様の執務室で構いませんか」
リュミエールがそう訊ねると、クラヴィスは声無くこくりと頷いて、壁際からゆらりと身体を起こした。ふたり連れ立って歩き出す。
聖地へ来る前から、リュミエールは楽器を弾くのが好きだった。ハープや横笛などが特に好きで、暇を見付けては独り演奏していた。
いつの頃からか、独奏を聞きつけたオリヴィエに合奏を申し込まれたり、クラヴィスやルヴァに演奏を求められたりするようになっていった。そういう人との交わりの中で楽に興じることは、リュミエールにとって良い気分転換になった。執務中の失敗から自己嫌悪に陥っている時や、他愛ない事で人と言い争いをしてしまった時でも、自然と心が落ち着いた。後ろ向きな考えから前向きな考えへと意識が変わり、気分が軽くなった。今日のように大切な人と逢えない時は特に、独りよがりな想いを諫め、まっすぐな心持ちを保つために、楽を爪弾きながら静かに過ごすことにしていた。
だから、今日これからクラヴィスの許で楽に興じることができるのはありがたいことだ、とリュミエールは思う。
クラヴィスが司る『闇』は、万物に安らぎを齎すと云われている。聖地一の問題児として名高い鋼の守護聖ですら、彼の人の庭では騒ぎを起こすことはない。庭木の間を分け入っていくクラヴィスを追いかけた時、鋼の守護聖の安らかであどけない寝顔に遭遇した。思いがけず微笑ましい光景に自然と表情を緩んだことを、よく覚えている。
リュミエールにとっても、クラヴィスと共に過ごす時間は、ルヴァと共に在る時間を除けば、一番と云って良いほどに心地良いものだった。しかし、だからといって自分から無理やり押しかけるといったことは、リュミエールの好むところではない。だからこそ、先刻のタイミングで声をかけて貰うことができてよかったと思う。
「…、ぁ…」
ふと閃いた考えに、リュミエールの足が止まる。その気配に気付いたクラヴィスが数歩先で立ち止まり、ゆるりと振り向いた。
「―――どうかしたか」
この人は、それを見越して待っていてくれたのだろうか。それとも。いや、きっと。
ふ、と緩む口許はそのままに、視線を送ってくるクラヴィスを見遣ってかぶりを振る。
「いえ、なんでもありません。…参りましょう」
リュミエールの返答に、クラヴィスは緩く首を捻る。
「そうか」
再び歩き出す姿を見詰め、リュミエールは佇んだまま深々と頭を下げた。
「―――ありがとう、ございます」
「………なんのことか判らぬ」
そっけない口調ではぐらかす、そんな彼の人なりの心遣いが、とても嬉しい。
「今日は、どんな曲がよろしいですか」
さりげない好意にはさりげない感謝を返すのが礼儀だろう。そうだな、と返ってきた調子の変わらぬ声を聞き、リュミエールの笑みが深まる。
聖殿の長い廊下には、傾きかけた日が仄紅い光と影を落としていた。
|