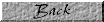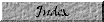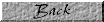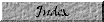|
初めて謁見の間に通された時は、かつてない程に緊張した。
『余り畏まらずとも良いですよ。ルヴァ、顔をお上げなさい』
微かな苦笑を声音の中に感じ、慌てて顔を上げた。はい、と思わず零した己の声は上擦っていて、列席していた守護聖達の方から聞こえてきたくすりという微かな笑い声に、顔が赤くなった。
『聖地での生活に早く慣れて、守護聖としての勤めに励むよう望みます。……皆も、出来る範囲で助けておあげなさい』
柔らかく優しげな声は、その時の自分にとってはただただ畏れ多い物で、何か言葉を返した気はするが、深々と頭を下げたこと意外は覚えていない。
気がつけば女王陛下は部屋を退席されていて、首座―――――光の守護聖に肩を叩かれ、漸く顔を上げた。
『後で聖殿内を案内する。自分の執務室で待っていてくれ』
『はい。…あの、宜しくお願いします』
自分をまっすぐ見る彼の強い視線に思わず姿勢を正してしまいながら、ぺこりと頭を下げた。頷く気配と共に部屋を出て行く様子に身体を起こし、自分もと扉へ向かう途中。
『……急がずとも良い、ゆっくり慣れることだ』
不意に後ろからかけられた声に少し驚いて振り向く。長い黒髪を纏わせた長身の男性―――――闇の守護聖が居た。威圧感は光の守護聖に負けず劣らず、といった感想を漠然と覚えた記憶がある。しかしその圧迫に似合わぬ励ましの言葉に一瞬返答が遅れ、気付いた時には扉の方へと歩み去ってしまった後。とにかく、と背中へ向けて頭を深々と下げた。
一番最後となってしまったが取り合えず執務室とやらに戻らねばならず、扉を押し開けて廊下へと出た。
緊張していた所為でかなり曖昧になっている今朝の記憶を手繰りながら、廊下を左へ右へと折れて進んだ。が、似たような意匠の廊下と部屋が続く所為か、どうにも見付からない。ついには見も知らぬ中庭のような所へ出てしまい、途方に暮れた。
『おや。こんなところでどうした。ジュリアスは部屋へ迎えに行かなかったのか?』
中庭の木蔭から声が聞こえてきた。ゆらりと光の下へと出てきた姿は、先刻謁見の間に居た守護聖のうちの一人のようだった。
『ええと、あの………緑…の、守護聖…の方、ですよね』
『ああ、そうだ。緑の守護聖をやっている。カティスと呼んでくれて構わんぞ。…で、こんなところでどうした』
すぐ近くへと佇み腕を組んで自分を見下ろしてくる笑顔はとても人好きのする顔で、少し肩の力が抜けた。
『それが、その……執務室の場所が判らなくなってしまって』
『迷っている、ということか』
事情はどうあれ迷ってしまったことが少し恥ずかしく、顔が火照る感覚を覚えながらもこくりと頷いた。
『来たばかりでは仕方ないさ。そう気にすることはない。―――――そうだな、俺が案内しよう』
『お願いしても……その、構いませんか』
申し訳ないとは思いながらも、誰かに案内して貰わないことには部屋まで辿り着けないだろうことは明白だったので、そう尋ねてみた。一瞬きょとんとした顔でじっと見られたと思った次の瞬間、彼は破顔して大きく頷いた。
『遠慮するな。案内くらいお安い御用だ』
ばんばんと肩を叩かれて思わずよろけてしまった身体を、彼は慌てて支えてくれた。済みません、と頭を下げて体勢を戻すと、彼は、もう少し身体を鍛えた方がいいな、と言って朗らかに笑った。少し強張っていた自分の顔が、その時、彼の笑みにつられて僅かに綻んだことが判った。
何も判らぬ道程を照らし導いてくれた人達が居る。知らぬうちに影で支えてくれていた人達も居る。そして、夢中で過ごす日々の最中、ぽっかりと口を開けた絶望の淵に足を取られそうになった自分へ手を伸ばしてくれた人が居る。
脳裏に浮かんでは消えていく皆の姿に口許を緩め、ゆっくりと眼を開く。揺らめくランプの火が作りだした己の影へと顔を向け、それから窓辺に映る己が姿を見詰める。
ランプの明かりを背負い影が落ちている己の顔をじっと見詰めていると、不意にノックの音が響き、来客を告げる侍従の声が聞こえた。告げられた名に自然と綻ぶ口許に気付いて目許を伏せ、顔をゆっくりと扉の方へ向ける。
「お通ししてください」
判りました、という言葉を残して玄関へと向かう侍従の足音が聞こえなくなってから立ち上がり、椅子の背に被せていた肩掛けを羽織る。金色の留め金で身体の前に合わせた布の端を留め、読みかけの本を本棚へと片付けた。
棚からポットを取り出そうとして、ふと留まる。替わりにグラスをふたつ取り出し、オープナーを引き出しから出して隣に置いた。そこで再度響くノックの音。
少し早くなる鼓動を感じながら、ひとつ深呼吸をして扉へと向かう。
知識以外に何の取り得もない自分のことを、とても気にかけてくれる人。初めて、大切にしたいと思えた人。
扉の前に立ち、ノブに触れる。訪れる期待に緩む表情をもう片方の手で撫でる。不安で仕方がなかった自分が今微笑んで居られるのは、彼のお蔭。その好意に何かひとつでも報いることが出来れば、と真剣に思う。
目の前で、侍従とは異なるリズムのノックが響く。はっと顔を上げ、ノブをぎゅっと握り直して、ゆっくりと回した。開く扉の向こうによく見知った顔を見つけ、更に微笑みが深まる。
「いらっしゃい。早かったですね」
「年が変わるのはそろそろだったなと思ってな。約束よりも早くなったが、大丈夫か?」
「―――――ええ、ええ……大丈夫です。立ち話もなんですから、中へどうぞ」
かつて己が居た地と聖地との隔たりから眼を逸らすことが出来ないならば、いっそ片時も忘れないで居よう、と決めたのは、彼の地を離れてから一年が経ったあの日。そのことを初めて話した時、彼は少し寂しそうな笑みを浮かべながら、けれど『そうだな』と頷いてくれた。そして、一年が経つ頃になると毎回、足を運んでくれるようになった。―――――隔たりをはっきりと認識することの辛さを分かち合う為に。
「一緒に飲もうと思って持ってきた。……少しくらいなら、付き合ってくれるか」
ラベルの無いボトルを受け取り、ええ、と頷く。多分今自分の顔には、少し泣きそうな笑みが浮かんでいる。そんな気がしたのは、彼が自分の頭を軽く撫でてくれたから。
己だけが取り残される感覚に夜毎涙した日々も確かに在る。けれど、かつて己が居た地の行く末を見守り光在る方へと導く、という希望を胸に、これまでを漸う歩んで来た。そして、この任が解かれるその日まで、変わらずにずっと歩んで行く。
グラスへ深紅のワインが注がれていく様を見詰める。彼がグラスを手にとってから、自分も同じ様にもう片方のグラスへと手を伸ばした。
「乾杯」
「―――――乾杯」
グラスの触れ合う音が小さく響く。交わされる笑みと流れる穏やかな時間。
彼と共に重ねていく幾千幾万の年越しを、決して忘れない。
彼が居なくなるその日がきたとしても、彼が分かち合ってくれたこの歩みを止めないために。
<FIN>
|