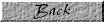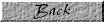|
「……私も、ですよ」
く、と握りこむ。背中に触れる手から、震えが伝わった。手の平で擦り上げるように揉むと頤が反る気配がする。濡れた、声。膝の内側を押すと、力に抗わず脚が開いていく。その間に身体を入れて服の合わせを肌蹴た。跳ねるように現れた昂ぶりに視線を絡めたまま、両手で弄玩し始める。
「あ、ぁ」
掠れた声に艶が乗っていく。付け根から揉み上げるように慰撫して幹を少しずつ擦り上げる。裏の筋を薬指で幾度も撫でながら親指できゅうっと締めつけるように握りこむ。指がようやく先の括れに到着した頃には、昂ぶりはすっかり硬くなり天を突くようにそそり立っていた。断続的に漏れる喘ぎに煽られたのか、ヴィクトールの熱も高まりを呈し始める。ふ、と息をつくと、括れに指の腹を押し当てて弾くように扱く。親指と中指で括れを辿りながら薬指で幹を擽る。空いた人差し指で先端の割れ目の周囲をぐるりとなぞった。
「…ぁっ…っあ、ぁ…っっ…」
上気した白磁の貌がゆるゆると左右に振られる。吐息に喘ぎがしっかりと混じり、受け止める悦の存在を伝えていた。透明な雫がぷつりと浮いてくる。それがみるみる大きくなっていき、幹へと伝い落ちそうになるほどになった。
「っや、あぁっ」
突然蜜口をきゅうっと吸い上げられて、腰がびくんと派手に跳ね上がる。こく、と動く喉。幹全体を擦り上げ始めると、さらにルヴァの喉が反り返った。唇は蜜口に吸い付いたまま、飴を舐めるようにまろみへ舌を這わせ、時折そのまま吸い上げる。片手は幹を、もう片方は更に下方へと降りていく。
くに、と密かに息衝く蕾を親指で押し込むように撫でる。
「ふっ…ん…っ」
びくりと肩が竦められる。それを気配で感じながら、ぐ、と昂ぶりを飲み込んだ。口腔一杯に頬張り息を呑むようにして、喉の奥で先端をきつく締め付ける。同時に先刻より高めの声が零れ落ちる。ず、ず、と上下するたびにびくびくと腰が蠢く。次第に自分から求めるように、好い処に喉が当たるように、腰が淫靡に動き始めた。彼を含むヴィクトールの口の端が、それに気付いて笑みに染まる。
蕾の入り口をくにくにと押していた指の先が、つぷ、と内部へ潜り込む。吃驚したのか、きゅうっと締め付けてくる感触が心地好い。そのまま爪だけが潜り込む深さでぐにぐにと蕾を刺激する。捏ねて掻きまわして中途半端な刺激でルヴァの感覚を翻弄する。
「ゃ……っだ、め…です…っ」
「……なに、が…ですか」
ふっと唇を解いて問い掛ける。直ぐにまた咥えられて吐息が乱れてしまう。包み込み締め付けながら幹を上下する唇の動きが次第に速く強くなり、ぐちゃぐちゃと卑猥過ぎる水音がひっきりなしに聞こえてくる。自然、零れる嬌声にも艶が増していく。
「…っめ……ゃっ…ぃ……」
言葉とは裏腹に、刺激を貪るように腰は蠢き震えは酷くなっていく。擦り上げが激しくなり、つ、と蕾に潜る指がさらに押し込まれる。両の太腿の間にあるヴィクトールの身体をルヴァの脚が引き攣るような動きで挟み込んだかと思うと、戦慄きながら力を抜いてしまう。極まったように繰り返される動き。
熱い猛りを一際深く呑み込み喉で締め上げ、入り口ばかりを弄っていた指が最奥へと突き立てられる。指の腹が奥のしこりに届いた、瞬間。
「っあ、ゃぁ…ああっ!」
ヴィクトールの広い肩を押さえつけながら、四肢を引き攣らせてルヴァが1度目の絶頂を迎えた。
無駄に生命を消費する行為。一度の交わりで幾億の灯火が失われる。
ただそれが『浪費』だとは言えない。誰にも言えない。……言わせない。
何にも代えることのできない、必要な行為。自分が自分である為。
赦しがこの身に在ると、確かめる為。
ルヴァの放った蜜を飲み干し、口元を拭いながら立ち上がる。ふらりと力を失って寝台に倒れこむ肢体を見下ろしながら、着衣を肌蹴て肌を夜気に晒す。躊躇無く服を落とした体躯は僅かに汗を含んでいて、その中心で息衝く熱はやはり天を衝かんばかりに反り返っていた。
余韻に浸りきったままヴィクトールをぼうっと見上げているルヴァに近付くと、その身体に残った着衣をするすると剥いでいく。下衣を取ろうとすると自然上がる腰の動きに、精悍な口元が微笑う。差し込む月の光に浮かび上がる肢体は、軍人然としたそれとは違い、白さが抜きん出て見える。添わされる手の平の褐色と相まってさらに際立ち、その上に仄かな紅が乗り艶やかさがいや増した。
寝台に乗り枕に背を預けて横たわりながら、呆けているルヴァを呼ぶ。ゆっくりと身体を起こす彼を引き寄せて、性急に唇を奪った。
唇を舐め歯の間を幾度も辿り口蓋を弄る。大きく口を開かせて喉の奥まで舌を這わせ、甘い蜜を交換する。厚い胸に上体を乗り上げて熱心に求めてくるその肩を撫で、背中を指でなぞる。背筋を下から上へと辿ると、ふるる、と肩を震わせ瞳を薄く開いた。
頬を挟み込んで顔を上げさせる。細く糸を引いて唇が離れた。腰へと手を伸ばして自分のほうへと引き寄せる。されるままルヴァは腰をヴィクトールの顔のほうへと寄せるけれど、其処から先の行動に躊躇する。
「ルヴァ、脚を」
手で脚を持ち上げ跨ぐように促す。顔を更に紅くして唇を噛むと、そろそろと片足を上げていった。眼前に晒されるルヴァの肢体に、喉が鳴る。顔を俯けたまま膝を下ろし、上体を丸めてヴィクトールの腹部に頬をつけた。するりと双丘を撫でる感触にも敏感に反応して、項垂れていた昂ぶりが顔を上げる。
晒される蕾に息を吹きかけながら、熱へ手を伸ばす。びくんと跳ねる腰を見詰めながらゆっくりと扱き始める。
「っあ」
ひくん、と仰け反る様子がよく見える。一度腰を高く上げさせて、昂ぶりを口に含んで湿りを与える。腹部に触れるルヴァの頬から伝わる振動、鳴き声を感じながら、舌を絡め蜜をたっぷりとそれに乗せて、ずるりと引き抜いた。
ぐちぐちと音をさせながら昂ぶりを両手で玩ぶ。強い刺激を与えるたびにひくつく蕾が物欲しげに見えてしまう。蜜口に爪を立てて抉りながら蕾へ舌を這わせると、もっと、と言わんばかりに腰を突き出してくる。その姿に、ヴィクトールが嗤う。
強弱をつけながら幹を扱くと、先端に這わせた指先にとろりとした感触が触れた。あとからあとから溢れてくるそれを掬い取り塗り広げてぐちゃぐちゃと捏ね回す。そうしながら蕾を割り中へ潜り込もうとするかのように舌を這わせた。
滴る蜜が門渡りを伝い昂ぶりの根元を潤す。くちゃりと音を立てながら入り口の襞をひとつひとつ丹念になぞり、時折舌を尖らせて中へと突き入れるように蠢かす。快楽に詰めていた息を吐く瞬間の緩みを逃さずに、より奥へと舌を送り込む。そのたびに甘い声が細く零れた。
|