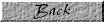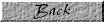|
上体を僅かに起こして、ぐったりと倒れこんでいるルヴァの腕を取る。触れた瞬間びくりと身体を戦慄かせた。与え続けられた深い快楽と2度に渡る吐精が、肌を敏感にさせているらしい。浅く息をつきながら身体を起こしてヴィクトールの脇に身体を横たえる。そのまま厚い肩口に顔を埋めてしまうかと想った肢体が摺り上がり、黄金の瞳に口付ける。瞳に、頬に、荒い息はそのままに口付け、最後に左眼にかかる傷痕に唇で触れた。
「ヴィ…ク……ト、…ール」
艶の入り混じる、掠れた声。頬を撫でて唇を合わせ、耳元に囁く。
「……舐めて…綺麗にして、くれますか」
左眼に口付けながらルヴァは小さく頷いた。身体をずらして腹部へ舌を伸ばす彼の胸へ、日に焼けた手が伸びる。きゅ、と摘むと、這わされた舌が微かに震えた。
ぴちゃぴちゃと己が放った蜜を舐め取る音が響く。紅い舌が覗き這い回る様は酷く卑猥で、その行為ですら悦を齎すのか、その表情が更に濡れていく。
はふ、と息を零しながら綺麗に舐め終えた貌が上がる。とろんと潤みきった表情に、ずくんと心臓を抉られる。
「ルヴァ…」
擦り寄る頬に囁く。ちろ、と耳朶を舐め名を呼ぶと、ふる、と戦慄く肢体の過敏さ。
「…ヴィ、ク……」
「どう…します?」
開いた唇から互いの舌が覗く。緩く合わされた唇の隙間から、ぴちゃぴちゃと触れ合い絡みつく舌が見えていた。だんだんと、深く密に口付けては、啄ばむように蜜を分ける。口付けながら、ルヴァは白い腕をヴィクトールの肩へと廻し、赤銅の髪を掻き混ぜた。未だ恥ずかしげな様子が消えない仕草でがっしりとした腰を跨ぐと、筋肉のしっかりついた太腿の上に腰を下ろす。
「も……っと」
謳うように囁く。
「…くだ…さ、い…っ…」
腰の斜め後方、寝台についていた手を片方持ち上げて、蒼の髪を撫でる。
「喜んで」
微笑いながら首を竦めるようにして白い喉元に口付ける。震えながらその唇を受け止めて、下ろしていた腰を浮かす。肩に廻していた腕を抜き、片手を胸に、もう片方を肩へとかける。
ふっと動きを止めてじっと黄金の瞳を見詰める。未だ身体の奥に渦巻く悦を確かに感じている貌が、縋るような視線を送っていた。
「貴方、は…」
零れた言葉に首を傾げる。膝を緩く立て、片方の手を腰から双丘へと滑らせた。ひくり、と腰を蠢かせながら、ルヴァが更に問う。
「……欲しい…です、か…?」
「勿論」
躊躇もせずに即答する。あまり肉のついていない臀部を撫で、奥まった処をなぞった。くち、と濡れた蕾に指先を咥えさせる。
「っあ、ふ…」
びくん、と腰が揺れる。細められた青鈍がとろりとした視線を流す。
「貴方だけが欲しい」
その台詞にまたひくりと肢体が戦慄く。
「わ……私、も…っ…」
く、と指を埋めると、呼応するかのように昂ぶりが張り詰めていく。途切れそうになる言葉を必死に紡いで、恋しい人の名前を呼ぶ。
幾度も、幾度も。呼ぶことで存在を手元に繋ぎとめるかのように。
引き抜かれた指の余韻に震える間もなく、腰を導かれる。入り口に当たる熱に瞳が濡れ、身体の奥から希求が競り上がっていく。
ぐ、と狭い入り口に強い圧力がかかる。先端が襞を広げつぷ、と内部へと侵入を果たす。
「っは…ぁあ…」
喉をやや反らし下肢から這い登る悦に肢体を震わせる。入り口をくちくちと幾度か擦り上げてから、内壁でその形をしっかりと捉えることができるくらいにゆっくりと、貫いていった。焦らされるような挿入に緩く首を振りながら薄い唇を噛む。
「ぁ…っゃ……あ、ぁ…あ…」
ぞくぞくと、背筋が粟立つような快楽が身体を侵し、理性を希薄にさせていく。ぴっちりと咥え込み、内壁は奥へ奥へと誘い込むような動きでヴィクトールを取り込む。身体の奥深くにまで焼けるように熱い楔を受け入れ、その楔を逆に熱く締め付ける。きつく抱き締めるように熱く包み込まれ、その快楽の最中、垣間見える貪欲に執着の匂いを感じる。
「ああっっ」
抱き込まれ胡座の上で突き上げられ、高く嬌声が上がる。濡れた声と熱い身体に、ヴィクトールの昂ぶりがまた容積を増した。
「っあ、はっ…っく…」
雫を一杯に湛えた瞳が金色を映す。激しい波のような快楽に攫われて、ふたりの境界が熱に蕩け互いに交じり合うような錯覚に陥る。ぐっぐっと突き上げる腰の動きに、蕾を擦り付けるような仕草が重なった。途切れず、永く長く尾をひく嬌声。
繋がった処から湿った音、肌と肌がぶつかる乾いた音。高まる熱に、止め処なく溢れ身体を浸していく快楽。激しさは、極まるとたゆたう波のように穏やかにさえ見え始める。
「ヴィ…ク、ト……ィクトー…ルっっ」
「ルヴァ……ル、ヴァ…っ…」
互いの名を呼び、嬌声の合間に睦言を繰り返す。
足りないなにかを埋める為、触れ合いを、深い繋がりを求めるけれど。
『言葉』では足りなくて。『身体』でも足りなくて。
未だ、その答えは見つからない。
「……ル……ヴァ…っっ!…」
「あああああっっ!!」
深く深く繋いだ身体が目も眩む程の快楽を生んで、蕩け出した思考が張り詰めた風船のように弾ける。幾度も穿ち直し存在を確かめて、繋がったままきつく抱き締めあう。
ゆっくりと、ゆっくりと、夜に潜む闇に冷えていく身体。それをまた暖めようと誘うのは、一体どちらからなのか。
きっとまた明日も、ルヴァは深緑のターバンを身につける。
奈落に沈んだ、たったひとつの答えを見つけ出すために。
了
|