|
道 程 〜 3 〜 |
|
トレイにティーポットとカップを2組乗せて持ち上げる。そのままくるりと振り返ると、黄金の視線とぶつかった。慌てて視線を反らし照れたような貌をした彼に微笑みかけながら、すたすたとテーブルへ戻る。 「どうかなさいましたか?」 「いえ、その……」 言葉尻を濁す黄金の瞳に視線を流し、とぽとぽと紅茶を注ぐ。ふわりと広がる好い香りに微笑みながら、かちゃりとカップを差し出す。どうぞ、と声をかけ彼の貌を覗き込むと、ひたりと視線が合わさった。 つ、と白い手袋を嵌めた手が伸びる。カップから離れた細い手首を、大きな手が捉えた。その手を下方へ引っ張られ、引き寄せられるまま一歩足を踏み出し腰を軽く折る。 「……ルヴァ様…」 顔が近付く。吐息が頬に触れる。捉まれていないほうの手をテーブルについて、ルヴァは瞳を閉じた。そっと触れる唇の感触は、泣いてしまいそうになるくらい、甘い。 「…ヴィクトール……」 声が掠れる。もう一歩足を踏み出して、テーブルについていた手を上げる。薄く微笑いながら、人差し指でなにか言いたげな唇に触れた。 「前に、お願い……しましたでしょう?」 切れ長の瞳が思い出したように少し開かれる。済まなさそうに視線を下げてしまおうとする動きを、唇に当てたままの指先と視線で押し留めた。 「ふたりだけのときは……」 乞うような口調に、困ったような貌でヴィクトールが微笑った。 「名前を…呼ぶのでしたね」 花が零れるような笑みが、肯定の印。 人とテーブルにつく時、向かい合うより隣り合って座ろうとする方が、より新密度は高いという。 ふたつ並んで置かれた椅子にふたりは座り、とりとめのない話をしながらルヴァの淹れた紅茶を飲む。ふと、暖炉の上に視線を留めたヴィクトールが口を開いた。 「ルヴァ……あの鉢は…?」 花でもなければ、木でもない。枝のようなものを挿してあるだけの、鉢。振り返ると、あぁ、と微笑いながら、ルヴァがその鉢を暖炉の上から取りテーブルへと持って来た。 「これは、挿し木をしているんですよ」 ほら、と指差された箇所に目をやると、小さい芽のようなものが生えているのが見えた。 「なるほど」 枝を土に挿し適当な環境を整えてやると、しっかりその地に根付き葉を茂らせる種類の植物がある。黄金の瞳が興味深げに鉢を覗き込む。実や草を利用する術に関する知識は豊富でも、育てるという方面にはほとんど縁の無い生活をしていた所為だろうか。初めて聞く不思議なその習性に、ヴィクトールは惹かれたようだった。 あるひとつの役割を与えられた細胞をその本来の役目から開放し、何者にも染められていない状態へと戻す。そうしてまた1から新しい個体としての生を生きる。……受粉もせず、実もつけずに。 その道を選び、自ら宿命として背負うことを決めたその胸中には、一体どんな想いが過ぎるのだろう。 「その、窓際に大きな鉢があるでしょう。あの木の枝なんですよ」 立派な枝振りの観葉植物らしきものを指し示され、振り返る。あまり馴染みのない種類のそれへと、目の前の小さい枝が育っていく。なんともいえない感慨を覚えたのか、ヴィクトールが頷きながら深く溜息をついた。 「実は、その木も最初はこの鉢に挿してあるような小さい枝だったのですよ」 告げられて、素直に驚く。がたりと椅子をずらして、半身になり窓際を振り返り感心したようにその植物を見つめた。 「その、私は本が好きなもので……」 「……?」 背中からかけられた言葉に、話の脈絡が見つけられない。つい、赤銅の眉を顰めてしまう。その様子を見て、ルヴァは慌てて言葉を続けた。 「あの、そのですねぇ、……本を読んだり、調べものをしていると、時間が経つのもついつい忘れてしまって」 テーブルの上に置かれていた本を何気なく手に取り、背表紙を愛しげに撫でながら続ける。森を散策するのは身体にもいいと言われたけれど、本を読むのに夢中になってしまい散歩になかなか出られなくて……。 「ああ、それで」 森林浴の代わり、という訳ですか。そうヴィクトールが言うと、ルヴァが嬉しそうに微笑った。外に行かない分、部屋に緑を置いたほうが好い、と言われたのだという。実際、あるとないとでは、身体の調子が随分違うものらしい。 常に野山を駆け回るような仕事に従事していた所為か、ヴィクトールはそういう実感が無い為ほんの少しだけ首を捻った。 挿し木から人の背丈ほどまでに育てるには、かなりの時間と労力、知識が必要になる。聖地ではあまり見られない種類の植物であれば尚更。いくら地の守護聖とはいえ、あるひとつの分野の末節まで行き届くほどの知識を持っているとは考え難かった。もともと興味を持っているような分野であればまだしも、お世辞にも積極的に行くとは言えない野山に育つ植物の育成方法とくれば、さらにその疑問は深まった。 「押し付けるばかりではなく、きちんと育て方も教えてくれたのですよ」 何処か懐かしげに、そのときのことを想いだしたのか嬉しげに、ルヴァは言葉を続ける。かちゃり、と、ヴィクトールの手元で、陶器同士が軽く触れあう音がした。 執務や読書、ほとんど趣味と化している自学研鑚の合間に、熱心な勧めもあり、前任の緑の守護聖から詳しい育て方を教わりながら育てたという。 最初はなんとも想ってはいなくても、付き合ううち、使ううちに愛着が湧いてくるということはままある。その木を育てたときも、同じような感覚があったという。 「だんだん、楽しみになっていったんですよ。明日はどれくらい大きくなるだろう、明後日は、という風にねぇ……」 観葉植物の場合は、その名の通り葉が主役なだけに、目に見えた変化というものはどちらかといえば乏しい。逆に草花などは、時として劇的とも言える成長を遂げて酷く驚かされることがある。聖地という特殊な時間軸の影響も否めなくはないが、それさえも、ルヴァにしてみれば興味を惹かれる対象になってしまうようだった。 成長した姿を目にすることを楽しみに、精一杯世話をする。自分がかけた手間を確実に反映して、凛とした姿を表す。そのときの達成感、感慨は言葉にし得ないものがあるという。 「調べ物をするときにも、同じような現象が起きるんです」 「……と、いうと?」 にこにこと笑みを絶やさない青鈍の瞳に、疑問を振り掛ける。 |
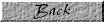
|

|
