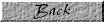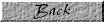|
どうして、気にするのかと。見上げる青鈍が問いかける。その答えは、クラヴィス自身、持ってはいなかった。彼こそが、その答えを知りたいと思っていた。だから、毎日地の守護聖の私邸に通い続けた。
いつになれば、判るのだろうか。その感情の向かう先に居たのがルヴァだったから、余計に判断能力が鈍ってしまっているのは事実。
………だから、これは、時間の問題。
控えめなノックにルヴァが応えると、食事を乗せたワゴンと共に侍従が部屋に入ってきた。数カ所の燭台にしか灯されていなかった火を分けて、部屋を明るくする。
クラヴィスは揺り椅子から離れ、夕餉の仕度が着々と整えられていくテーブルへと近付くと上座脇の椅子へ腰を下ろした。ルヴァを呼ぶと、渋々といった風に揺り椅子から立ち上がり、上座へと腰を下ろす。ふと廻らされた彼の視線の先には、聖地ではあまり意味を成さない暦。
「ああ…そういえば」
ぽつりと呟くと、スープを注ぎ分けていた侍従に、倉からワインを一本持って来るように言いつける。
「取り敢えず、これだけ先に頂きましょう」
珍しく食事をとる気になったルヴァが、スプーンを取る。同じくスプーンを取り暖かな湯気を上げるスープ皿へと銀のそれを沈めた。
口数少なく、時折部屋に食器の触れ合う音が響く。と、ワインとグラスを手にした侍従が戻ってきた。掬う手を止め、コルクを開けさせると、クラヴィスへグラスを差し出してルヴァは首を傾けた。
「…少しくらいなら……飲む、でしょう?」
「……貰おう」
差し出したグラスに滑りこむ、透明な流れ。今日の主菜は魚だったから、侍従がわざわざ白を選んできたのだろうか。
自分のグラスに注ぐと、ルヴァはグラスを目線と同じ高さに掲げた。何に乾杯するつもりなのか首を捻りながら、倣うようにクラヴィスもグラスを掲げる。
「貴方の誕生日に、……乾杯」
久しぶりに見た鮮やかな笑顔と、その台詞に、クラヴィスは息が止まりそうになる。
「な……」
こく、とひとくち飲むと、絶句してしまっている黒髪に、ルヴァがもう一度微笑いかける。先刻の鮮やかさは既に姿を潜めてしまっていて、消えそうな風情だけが其処にはたゆたっていた。
「…いえ、ね。暦を見たら、貴方の誕生日だったから。……気に障ったなら、謝ります」
「いや…私こそ、済まなかった。……ありがとう」
視線の置き場に困り目を伏せながら、手の中のグラスに口をつけた。
アルコールの所為だけではない、確かな熱が、クラヴィスの身体の奥に宿る。
その存在に振り回されず、しっかりと向き合うことができるのは、きっともうすぐ。
「もう一杯、如何ですか」
「……」
空になっていたクラヴィスのグラスに気がついてルヴァがボトルを傾けた。つ、と手が動き、クラヴィスがグラスを近付ける。
とくん、とくん、とワインが注がれ、香気が周囲に広がっていく。
「…もっと、ちゃんと食べろ」
「はいはい」
殆ど手のつけられていない主菜の皿を見咎めたクラヴィスの声に、ルヴァが苦笑しながら返事をする。
きっと、明日もクラヴィスは、ルヴァの私邸へ脚を運ぶ。
ふたりの思いの行く末を、総てが見守っている。できることならば、幸あらん、と。祈るような月が地の守護聖の私邸の上、煌いていた。
了
|