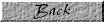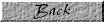|
勧められた椅子に腰掛け、ややして出された紅茶に手を伸ばす。テーブルの向こうには、彼の普段を知っている者ならきっと、目を丸くする程に珍しい、柔らかく優しげな微笑み。火傷してしまわないよう気をつけ香りを楽しみながら紅茶をひとくち飲み、かちゃりとカップを置いてその微笑みを同じく微笑みながら見詰める。
「……どうか、なさいましたか…?」
首を傾げる仕草へ曖昧に笑みを返しつつ、ルヴァはごそ、と袂を探る。
「これ……を、貴方に……」
差し出されたのは、手の平に乗る位の細長い箱。首を傾げながら取り敢えず受け取り、どうして、とあからさまな疑問を乗せて視線を流す。その様子を見詰めながら、先刻端末室で見た苦笑がもう一度白磁の面に現れた。
「…今日は…何月何日だか……判りませんか?」
白い指がついと壁を指し示す。その先には数字だけが並ぶ簡素なカレンダー。女王試験の間は下界と聖地の時の流れの整合が図られる。そのため、常ならば意味のないそれが、今この時だけは意味を成すものとして認知されていた。
振り返るようにしてカレンダーを見詰め、此処暫くの記憶とその日付とを照らし合わせていたエルンストの首が、小さく傾ぐ。
「12月……30日、ですか…?」
小さい笑みと共に頷きが返され、それでもまだ訝しげな碧の瞳に、苦笑めいた貌が映る。
「貴方の…誕生日、ですよ…?」
はた、と動きが止まる。もう一度カレンダーを見詰めた貌が、碧の瞳が、微かな驚きを載せて振り返る。
「……確かに……そう、ですが…」
当の本人が忘れてしまっていたような事を、覚えていてくださったんですか、と。渡された細長い箱を手にしたまま僅かに見開かれた碧の瞳に、ゆるりと微笑む。
「だって…貴方のこと、ですから。…貴方だって……私の誕生日を、覚えていてくださったじゃないですか…?」
私も、自分の誕生日のことは……すっかり忘れてしまっていましたけれどねぇ、と小さく微笑う。その瞳の隅に潜む僅かに悪戯な色に、つられるように微笑ってしまう。
「それでは……これは、誕生日の…」
「……プレゼント、です」
こくりと頷きを返しつつ、開けてみてください、と促すルヴァに小さく頷きを返し、余り飾り気の無い包みを開く。出てきたのは用途に覚えのあるプラスチック製の箱。
「眼鏡…です、か」
かち、と小さい音を立てて開かれる箱を覗き込む。こくりと頷く姿が視界の隅に映る。落とした視線の先に現れたそれは、趣味の良い流線を描き、白い光を弾いていた。
「以前……伺った通りの屈折率で作って貰いましたから…多分大丈夫だと、思いますけれど…」
少し自信なげに呟く彼に笑みを向け、掛けていた眼鏡を外すとそれを手に取り、試しに掛けてみる。
眼鏡のレンズ越しに見えるルヴァの貌が、期待と不安に揺れている。度は合っているだろうか、気にいって貰えるだろうか、要らないと言われてしまわないだろうか。手に取るように判ってしまう心の動きに小さく微笑み、ほんの少しだけ首を傾ける。
「……似合いますか?」
微かに明るくなる表情。とても、という言葉と共にこくりと大きく返される頷き。
「ありがとうございます…よく、見えますよ」
一休みをしようとテーブルに置いた眼鏡を、興味深げに手にとって眺めていたルヴァをなんとなく思い出す。目の上に翳して景色を見たりしながら、どれくらいの屈折率なのか、と聞かれたのは、随分前。ただ聞かれるままに答えたことだったけれど、あのとき既に、今日のこの日が頭にあったのだろうか。
返されたエルンストの言葉に、ぱあっと青鈍の瞳が明るくなる。その胸元には、過日エルンストが贈った銀細工のルーペが部屋の光を反射していた。
双方共に研究家肌の人間で、一旦研究に没頭し始めると寝食を忘れることもしばしば。周囲が見えなくなることで有名な所もやはり、似通っていて。
そんなふたりが。互いの事に関しては、研究よりも惹かれているという事実。
森の湖のほとりで思索を重ねるその合間、ふと碧の瞳を思い出し、その記憶を辿るという行為に随分な時間を費やしてしまう。若しくは、端末室でデータの解析をしている最中、いつもなら処理を待ちながら次の行程を考えるのが常だったのに、柔らかな微笑みを乗せる青鈍の瞳を思い出し、次に逢える日へ思いを馳せてしまう。そんなことが、日常茶飯事になってきていて。ふと我に返った瞬間、それぞれに苦笑を零しつつも何処か幸せな想いに浸る。
そんな、日々。
手元に置いてあった眼鏡入れに、先刻まで自分が掛けていた眼鏡をしまい、その様子を見詰めるルヴァに微笑みかける。
「今晩は……泊まっていかれますか?」
新しい眼鏡を掛けた、少しだけ見慣れない雰囲気のエルンストを見詰めたまま、白磁がゆるりと綻び、ええ、と頷きが返される。
「一年に一度の……折角の日、ですから」
ありがとうございます、と笑みがもう一度返される。夕食にしましょう、と立ち上がりシンクへ向かうエルンストの背中を、同じく立ち上がったルヴァが追う。
「あの…私も、お手伝いします…」
指、怪我しないでくださいね、とからかうような声が返り。ややして小さな微笑い声が重なり合って居間へと漏れてくる。
食事を作ることが目的ではなく、ふたりで居ることが、最大の目的。
互いが一番の存在だということを確かめる夜が、ゆっくりと更けていった。
了
|