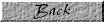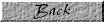|
「もう貴方とは一緒に入りません〜」
「えぇ〜そないつれないこと言わないでくださいよ〜っ」
恨めしそうなルヴァの声に応えて、若干おろおろとした調子で返す。まだ冷めない熱を振り払うようにふるふると頭を振り、目の前の大きい枕にぽすんと顔を埋めた。そろりと少しだけ顔を上げて視線だけをチャーリーに送る。
「あ」
「…なん?」
瞬間ぱちんと出合った彼の目線と笑顔にまた顔を紅くして、ルヴァはごそごそとベッドに潜りこんでしまう。
その様子をじいっと見詰めながら、今にも蕩けてしまうのではないかという程にふやけた笑みを口元に乗せて、チャーリーは手にしたグラスのなかへ氷をひとつふたつ落とした。
寝台の縁を沈ませてチャーリーがルヴァの髪に顔を近付ける。まだ少し濡れているそれに引き寄せられるように口付けてしまう。
「……ひゃ…っ」
先刻の名残か、びくん、と首を竦めてしまう彼の反応に、更に貌が蕩けていく。ベッドから引き剥がしてもう一度きつく抱き締めてしまいたくなる衝動をなんとか押さえ、手の中のグラスを持ち直す。
「水、持ってきましたから、……はい」
少しだけ離れた彼の気配を感じて、そろりと貌を上げる。案の定真っ赤に染まっている顔、その表情がまたチャーリーを密かに煽ってしまう。
ぐっと堪えながら、見上げてくるルヴァににこりと微笑いかける。幾らか警戒しながらも身体を起こそうとルヴァが身動ぎした。
「!……っ…」
小さく声を漏らし、びく、と身体を戦慄かせて眉を顰めると、起き上がろうとした筈のルヴァはそのままぱったりとベッドに倒れ込んでしまった。驚いて顔を覗き込もうとするチャーリーに、再びルヴァの恨みがましい視線が注がれる。
「貴方の所為ですよ〜もう〜〜」
上気した肌、艶やかな肢体、それに魅入られて酷くしてしまったチャーリーも悪いのだけれど、居直って誘ったルヴァにも責任の一端はある。あるのだが、それを素直に認めることができないのも、仕方の無いことで。
「したら、責任とって飲ませてあげます」
水をひとくち含むとサイドボードにグラスを置き、ルヴァの頤に手を添えて上向かせる。じっと見詰めてくる瞳が『ええでしょ?』と問うているのを確かに感じながら、ルヴァは一瞬身を引こうとしてしまう。それを逃がさないよう項にも手が伸ばされ、くっと頭を固定された。
重ねて首を傾げる彼の仕草にくらりと眩暈を覚える。本当のことを言えば、恥ずかしくて辛くて堪らない。けれど、それでもやっぱり彼が欲しいと想う自分が居る。
「……やっぱり重症ですねぇ〜」
ぽつりと落とされたその言葉を聞き咎めて、チャーリーが更に首を傾げる。それをさらりと無視して、ルヴァはすうっと瞼を閉じた。項と頤にかけられた指が微かに震え、彼の動揺が伝わってくる。心のなかで苦笑すると、自分からほんの僅かだけれど顔を上向かせた。
かけられた指の力が強くなる。
「…ん…っ」
合わせられた唇の隙間から、冷たい水が流れ込んでくる。その両極端な感触に、またくらりと眩暈がした。
『彼』だから、好いと想った。
含んでいた水を全て流し込むと、名残を惜しむように唇を舐め顔を上げる。離れる瞬間、舌にえもいわれぬ甘さが残る。こくりと喉を鳴らしながら、自分の胸に頭を預けてくるルヴァを見下ろした。
けぶる睫、上気した頬、紅い唇。自分と同じ男である筈なのに、どうしてこうも惹かれるのか。
そっと額に口付けると、彼のほうから腕を伸ばしてしがみついてくる。それに応えるようにチャーリーも腕を伸ばして抱き締めた。腕の中に確かなぬくもりを感じながら、ふと想う。どちらが抱き締めて、どちらが抱き締められているのだろうか、と。
まるで判らない危うい境界線。だからこそ、意味があるのかもしれない。
『彼』でなければ、意味がなかった。
「末期やなぁ」
「え?」
囚われきっている自分を再確認して苦笑する。それでも居心地の好いこの関係を、諦めるつもりも失くすつもりも毛頭無い。
訝しむように見上げてくるルヴァを、もう一度きつく抱き締める。
「泊っていってもええです?」
「そのつもり、なんでしょう?」
えへへ、と頭を掻くチャーリーに、ふふ、とルヴァが微笑う。
ルヴァを抱き締めたままぱたりと寝台に倒れ込む。つられて身体を倒され、走った痛みに思わず顔を顰めてしまう。
「あ、す、すんません〜…だいじょぶです?」
「……そう思ってくださるのなら、次は手加減してくださいよ〜」
「え〜…せやかて――――」
喩え重症でも、ふたり一緒だったらいいかもしれない。
腕の中のぬくもりを抱き締めて心を寛げ、耳元で優しく響く鼓動に頬を緩めながら、ふたりの密やかな笑い声が部屋の中に満ちていった。
了
|