|
護りたいひとが居るということ 〜 2 〜 |
|
聖地に来た時点で一番年若かったランディ。直ぐ上の守護聖といっても3年の歳の差は結構大きくて、一方的に玩具にされてしまい不貞腐れることもしばしばだった。なかには剣の稽古をつけてくれたりする人も居たが、やはり一緒になって行動したり趣味を共にするというような、所謂『友人』という関係にはどうしてもなれなかった。 そんな時、新しい守護聖就任の話を聞いて、密かに一番喜んだのはランディだった。 ランディよりひとつ年下の守護聖。今度こそは色々な話のできる対等な友人が作れるかもしれない、という期待。新しく来る歳の近い守護聖のことばかりが気になって仕方なかった。 前任の鋼の守護聖とは、女王の下に集う同じ守護聖として或る程度の行き来はあったけれど、聖地で過ごした年月の短いランディにしてみれば、それはほんの少しの寂しさを伴う程度のものでしかなくて。 急な守護聖交代の裏に横たわる複雑な事情。数限りない衝突を乗り越えて、ふたりは『好い喧嘩友達』という関係を築くに至った。そして新しい緑の守護聖が聖地へやってきて、『御子様達』というあまり嬉しくない名称で呼ばれることになる。 そうして仲良くなった彼等との行き来の中、かなり頻繁にその姿を見かけるようになったのが、地の守護聖ルヴァだった。 守護聖としての教育を受けられなかったゼフェル。その教育係にルヴァが任命されていたことが、一番の理由。 最初の数ヶ月は、話をしに行こう、遊びに行こうとするとまず間違いなく、ゼフェルの傍にはルヴァが居た。反抗期が10も20も重なってやってきたような状態のゼフェルに手を焼きながらも根気強く通い、少しづつではあるが心を開き始めた後輩へ熱心に講義をしているらしかった。 前緑の守護聖と仲がよかった所為か最初からルヴァにとても懐いていたマルセルなどは、手製の御菓子を土産によく御茶を飲みに来ていた。ルヴァがゼフェルの私邸へ講義に来ていると当然マルセルも3時の御茶のセットを持参して鋼の守護聖の私邸へと出かけていく。彼に会おうとするとやはりルヴァに逢うことになった。 全く接点の無い人だった。 執務の上で関係することがあるかというとほとんどなく、ロッククライミングを趣味とするくらい活動的なランディに比べれば、偶に釣りに出かけるだけのルヴァなどは戸外で行き会うことすら稀で。 下手をしたら平気で1週間やそこらは会わないで擦れ違うような関係でしかなかった。 それが、ゼフェルとマルセルを接点にして、少しづつ変わっていく。 2週間に1度会えば好い方だったのが、1週間に1回、3日に1回、という風に、ルヴァに会う回数が増えていく。そうして回数を重ねる度、ルヴァに対する認識が新たになっていった。 ただぼんやりしているだけに見えた姿は深い思索のためのものだと理解り、なかなか結論を言わない優柔不断さも、裏を返せば自分の言葉の重みを知っているからこその慎重さで。のんびりしていてもどかしく感じた喋り口調でさえ、穏やかな春の日差しのように心地好い響きに聞こえるようになる。そしてまた彼の口から語られる知識の深さと広さには、今更のように驚かされた。『流石は智慧を司る地の守護聖』、などと不敬にあたるようなことすらも思ってしまう。それ程に、彼について知らないことが多過ぎた。 それよりもなによりも、暖かく全てを包み込めるのではないかと思う瞳の優しさと懐の深さに、ランディは惹かれていった。 それまで親しくつきあってきた人達いずれとも違う人柄。ランディの言葉や行動を茶化さず、質問を真摯に受け止め、時には優しく時には厳しく応じてくれる。次第に、ランディにとってルヴァは、父親や兄のように頼ることの出来る存在になっていった。 その一方で、危なっかしげな足取りに思わず手を差し伸べたくなるような人でもあって。その両極端な内面を見るにつけ、ランディの心の中でルヴァの存在感が大きくなっていった。 ゼフェルと一緒にルヴァの講義を受けることになった時のこと。 「おめー、最近よく来るよな」 そう言われた瞬間、心臓がどくんと脈打った。 「え……いや、俺だってまだ知らないこと沢山あるから……」 ふぅん、とつまらなさそうに曖昧な相槌を打って、ゼフェルがテーブルに肘をついてあらぬ方向へ視線を流す。どうしてか早くなる鼓動に複雑な表情をしたまま、ランディは胸へと手を当てた。 出されていた問題を考えるふりをして、視線を遠くに投げる。と、隣の書庫の扉の隙間にルヴァの姿を見つけた。どくん、と更に跳ね上がる鼓動。顔が熱いような気がする。ゼフェルに気付かれる前に、テキストに視線を戻さなければと思うけれど、視線が外せない。 視線の先で、本へと視線を落としていたルヴァが顔を上げた。あ、と思った次の瞬間、ランディに気がついて青鈍がにっこりと微笑う。 ランディはその時初めて、ひとりの人間として、ルヴァに惹かれている自分を自覚した。 |
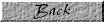
|

|
