|
護りたいひとが居るということ 〜 4 〜 |
|
キン、と高い音を響かせて、剣がぶつかり合う。ふたつの影が重なり、瞬時に飛び退る。 「今日はここまでにしようか」 正眼に構えていた長剣を鞘に収める。同じく剣を鞘に納めた後輩の頭をぽんぽんと軽く叩くと、隣をすり抜けて庭先の長椅子に腰を下ろした。息をほとんど乱れさせていない先輩を眩しそうに見上げ、その隣に座る。 運ばれてきた御茶をひとくち飲む。テーブルに肘をついて自分を見ている彼に気付いて、首を傾げた。 「……あの、どうかしましたか?オスカー様」 にっと微笑うと自分の前に置かれたカップを手に取って喉を潤す。不思議そうな貌をしているランディをじっと見据えると、もう一度口元に笑みを乗せた。 「ランディ、御前、強くなったな」 「……え…」 思いがけない言葉に、更に青い瞳が丸くなる。 「ここのところ暫く……稽古する度確実に腕が上がっていっている」 「ほ、本当ですか?」 ここまではっきりした評価を貰ったことは今まで殆どなかっただけに、浮き立つような気分で聞き返す。ああ、ともう一度頷きながら、オスカーは背凭れに身体を預けた。 「以前とは比べ物にならないくらいの伸びだな。自信を持っていい」 明確に肯定をされて、ぱあっと表情が明るくなる。自分の手を見ながらにこにこと嬉しそうに貌を綻ばせた。 頬杖をつきながらそんなランディを見ていたオスカーが、すいっと手を伸ばしてその額を突付く。 「……もしかして、護りたい相手ができたか?」 きょと、と目を丸くしてオスカーを見返す。直ぐに貌を真っ赤にして口をぱくぱくと開閉させる姿に、ぷっと失笑してしまう。 「別に悪いとは言ってないだろう。俺は大いに奨励するぜ」 先のオスカーの言葉を無様に思い切り肯定してしまったことに気付いたのか、貌を紅くしたまま複雑な表情をしてランディは黙り込んでしまった。 流石に悪いことをしてしまったか、と、オスカーは手を伸ばし宥めるように栗色の髪をくしゃくしゃと掻き混ぜた。 「護りたい相手が居る、ってことは、胸を張っていていいことなんだぞ」 「…………」 からかった訳じゃないからそうむくれるな、と、苦笑するオスカー。 「それにな、『護りたい相手』ってのができると、人は強くなれる」 「強く…?」 こくりと頷く彼の貌は、酷く真剣だった。背凭れの上端に両腕をかけて、ぎしっと凭れかかる。首を傾げるようにランディを見ながら、言葉を続ける。 「今よりもっと強くなりたいだろう?……大事な誰かを、護れるように」 「……はい」 ふっと微笑うと、気負ったように膝で拳を握り締めるランディの背中を強く叩いた。びっくりして目を白黒させながら軽く咳込む彼を、何処か羨ましげな氷色の瞳が見詰めた。 「よし、もうちょっと稽古つけてやるか」 「え、ええ〜〜っっ??」 慌てたように腰を浮かす後輩に貌を近付けて、据わったような目でじいぃっと見る。 「……まさか、あれくらいの稽古でへばったとか言わないだろうな」 「………ま、さか…そんなこと、ある訳ないじゃないですか」 迫ってくるオスカーから身体を引くようにして、引き攣った笑みを浮かべながらようやくそれだけ言う。すると楽しそうに氷色の瞳を細めて微笑い、すっくと立ち上がる。 「よし、もう一本来い!」 「…っは、はいっ」 前を歩く紅い髪を見上げながら、ランディの脳裏にはおっとりとした彼の姿が浮かんでいた。 あの人が居れば、もっと強くなれる。あの人の為に、強くなる。どんなものからも、あの人をきっと護れるように。 眼下で、白い肢体が悦にうねる。 「ぃ……っラ、ン…ディっっ」 強く腰を打ち付けると、びくんと身体を跳ね上げて嬌声を零す。 今はただ、一緒に居たい。隣に居たい。この人を見詰めていたい。 ………そして、護りたい。 これから先は、どうなってしまうか判らないけれど。 乞われるまま膝の上に抱き上げて、下から突き上げる。蕩けそうな声を上げながら、しなやかな筋肉のついたランディの肩に縋りつき、自ら腰を揺らめかせる。 「ぁ…っく、ぅ…っ」 きつい締め付けにまた飛んでしまいそうになるのを必死に耐える。どうにか激情を押さえ込んだ視線の先で、紅い舌が同じくらい紅い唇を舐めていった。誘われて唇を寄せ、深く口付ける。 腕の中のぬくもりをしっかりと抱き締める。 自分の力で、確かに護っていけるように。 了 |
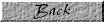
|
