|
蛹が孵化する日 〜 2 〜 |
|
植えた苗の根元へスコップで土を盛り、軽く手の平で押さえる。葉の様子を見ながら手探りで傍らの如雨露を手に取って、湿らせる程度に水をやった。最後の一本。嬉しそうな笑顔と共に息をひとつついて、綺麗に並んで日の光を浴びる苗を見渡した。 「これ、裏の小屋に戻してくる」 「ん、ありがとっ」 嵩張る箱をよいっと持ち上げすたすたと歩いていく長身に声をかけて、そのまま見送る。少し首を傾げながら暫しランディの背中を見て、それから自分を見下ろす。唇を引き結んで、今度は小さく溜息をついた。 「僕ももうちょっと背が欲しいなぁ……」 「…なんか言ったか」 相変わらず機嫌の悪そうな貌でゼフェルが声をかける。ふっと上げた薄紫の視線の先で、地面に転がっていたスコップを拾う。 「今日はコレで終わりなんだろ。……洗ってきてやる」 片手にはスコップ数本、もう片方で苗の入っていたビニル製の鉢を重ねて抱えていた。滅多に無い申し出にマルセルが目を丸くすると、小さく舌打ちをしてくるりと踵を返した。 「悪かったな、柄にもねぇこと言って」 「そんなことないよ!…ありがと、ゼフェル!」 立ち上がりかけるマルセルを置いて、屋敷脇の水場へと足を向ける。2回目の舌打ちが遠く聞こえた。 もう一度ぺたりと座り込んでそよぐ葉を眺める。つと顔を上げて青空を仰ぐと、ふらりと視線を泳がせた。その先には、樹の幹に凭れて寝息をたてる蒼の髪。 「ルヴァ様…」 くしゃ、と貌が綻ぶ。立ち上がると服についた土を払って木陰へと近付く。直ぐ隣に腰を下ろすと、伏せられた瞼をじっと見る。風に流されて頬にかかった一筋の髪に手を伸ばして、そっと払った。 「……綺麗」 ほうっと息をついて、見蕩れながら首を傾ける。 初めて逢ったときから、そう思っていた。唯綺麗なだけのひとなら他にも沢山居るけれど、『綺麗』で『優しく』て『あったかい』のは、目の前のこの人だけ。初めての場所、初めて見る人達、捉え所の無い自分の能力。全くの新しい生活に不安になっていた心を溶かしてくれたのは、あの人の笑顔。 力がまだ不安定だったマルセルに代わってカティスが辺境の惑星の祭礼に出かけてしまい、広い屋敷に独り残された夜。泣いてしまいそうなくらい不安で寂しくて、つい舘を飛び出して夜道を歩いていた時、偶然帰宅途中だった彼に出会った。慌てて涙を拭い挨拶をするマルセルを私邸に誘い、暖かいミルクを差し出したあの人の柔らかい笑顔。 ぱちぱちと時折はぜる暖炉。漏れてくる暖かい橙色の光。なにも言わずにただ隣に座り、御茶を飲むルヴァ。ゆっくりと流れる沈黙が、そのときはなんだかとても優しくて。 |
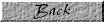
|

|
