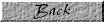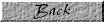|
マグカップの底が見え、マルセルの喉の奥から時折零れていた嗚咽もすっかりなりを潜めた時のこと。
「……今日は、泊っていきませんか?」
客間をひとつ用意させましたから。そう言ってにっこりと微笑んでくれたその貌が、泣きそうなほど暖かくて。こくりと頷いた金髪をゆっくりと柔らかく撫でる手の平。じんわりと優しさが染みていくのがわかって、ぽろりと膝の上に涙が一粒零れ落ちた。
ぐっと涙を堪えるマルセルを促して、客間へと案内する。用意されていた夜着に着替えてベッドに潜りこむ。見上げた先に、ルヴァの笑顔。部屋の明かりは落とされ、ベッドサイドのランプに照らされた微笑になんとか微笑い返す。白い手が伸ばされて、もう一度頭を撫でる。同時に落とされた、台詞。
「泣きたいときは、泣いていいんですよ」
菫の瞳が大きくなる。額から髪を掻き揚げて、もう一度にっこりとマルセルに微笑みかける。
「大丈夫、ですからね」
貴方は、貴方のままで、いいんですよ。その言葉に、ぽろ、と涙がまた零れ落ちた。堰をきったように、次から次へと零れていく涙。しゃくりあげる金の髪をゆっくりと撫で、宥めるように上掛けの上からとんとんと胸を叩く。
暖かい言葉と、それ以上に雄弁な微笑み。
マルセルが泣き疲れて眠ってしまうまで、優しい手の平は金の髪をずっと撫で続けていた。
その日から。
まだ幼い胸の中に、ルヴァの姿が映り始めた。
自分よりも遥かに大人の彼は、考える、ということに特に秀でている所為なのか、行動力という言葉にはやはり無縁のようだった。聖地での時間を重ねるに従い、何処か危なっかしいところのあるルヴァを『護りたい』という気持ちがマルセルの心のなかで大きく育っていく。
その想いは、未だ変わらず。
大切で、大切で。
居なくなってしまうことなど考えられないくらいに。
木陰から零れ落ちた日の光がルヴァの頬に乗る。白い肌。柔らかそうな蒼の髪。先刻触れた髪の感触が、指先に鮮やかに残っている。
風が吹く。こめかみから垂らされたターバンの端が揺れる。つと指先を伸ばして裾を取り、そうっと口付けた。何気なく取った自分の行動に、内心鼓動を跳ね上げながら、直ぐ目の前のルヴァを見詰める。
白い頬、震える睫。柔らかそうな頬の線、紅い唇。
芝に手をついて、もっと顔を近くに寄せる。
吐息を、直ぐ近くに感じる。紅い………くちびる。
|