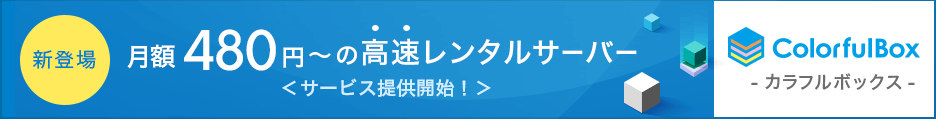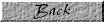|
セイランに割り当てられた居住区画の扉の前で、ひとつ深呼吸。こんこん、と入室を問うと、開いてますよ、と遠い声が響いてきた。幾度も繰り返されてきた、手順。
「まだ、起きてたんですか」
「貴方もね」
向かったキャンバスから顔も上げずに応える。棚から備え付けのポットを取り出し水を入れて火にかける。やはりこれも、いつもの光景。
しゅんしゅんといい感じの音が聞こえ始めた頃、ようやくセイランが筆を置いた。ルヴァの座るところからは角度的に見えない位置に置かれたキャンバスを、上体を引いて暫く眺め、すくっと立ち上がるとテーブルへと近付く。すぐ隣に立った影を見上げる青鈍に、ふいっと蒼の髪が落ちた。大事に、大事そうに、触れるだけの口付け。
「……御茶、淹れますね」
離れた唇と呼応するように開いた唇が、冷静にそんな言葉を紡ぐ。肩眉を上げて薄く形の好い唇から溜息がひとつ零れた。
「貴方のそういうところが、嫌いですよ」
口調は笑っている。その台詞を聞いて、ルヴァが細い目を少し大きくして微笑った。紅茶を満たした簡素なカップをふたつ手に、テーブルに戻る。椅子に座るとその背に彼が回りこんだ。不思議そうな顔で振り返る背中にふわりと触れる温もり。肩に腕が廻されて、抱き締められる。
傍らで湯気を上げる紅茶。緩い抱擁に薄っすらと瞳が閉じる。
「本当に貴方は『大地』みたいだね」
ふと口に出した自分の言葉が妙に気に入らなかったのか、苦々しい貌で空を見詰める。更に身体を寄せて、髪にかかった布を噛んだ。
何処に居ても、なにをしていても。背中から自分が抱き締めていても、何時もその腕で抱かれている。守っているようで、護られている。口惜しくもあり嬉しくもあり、そんな複雑な感情に時折襲われる。
『大地』は全てを抱擁し許容して、その懐に抱き締める。一番関係が深く、時として同義のように扱われる『緑』も例外ではない。逆に、大地の恵みが無ければ、『緑』は芽吹くことも叶わない。『大海』でさえ、結局は『大地』の手の中に収まっている。
全てを手にしたものは、即ち全てを知っている、ということになるのだろうか。それならば、『地』の守護聖が『智慧』を守護することもすんなりと頷くことが出来る。全てを識り、その上でなお全てのものを限りなく柔らかく抱き締める存在。
『自分』を、そのままの『自分』として、受け止めてくれる、存在。
ただし、『力』としては純粋に機能するその『性質』も、『守護聖』という形を取ると弱くなる。ひととしての迷い、怖れ、不安……幾多の波を越えて、初めて境地に至ることが出来る。
或いは、ただひとつの『理解』、それを表現した『言葉』を糧にして。
「居てくれるんでしょう?」
耳元で囁く声は、確かにルヴァを必要としていて。
「そのつもりがなければ、こんな時間に伺ったりはしませんよ」
返す台詞の奥底にも慾が存在していることに気付いた透明な瞳が、楽しそうに微笑う。
「だから、貴方は嫌いだ」
言葉とその裏に秘められた意味は、時として相反する姿で現れる。涼やかな声と共に笑ったセイランの唇が、もう一度ルヴァのそれを塞ぐ。
「嫌いで、嫌いで……好きなのかも、しれないですね」
密やかな睦言は鼓膜を響かせることなく、喉の奥に消えていった。
了
|