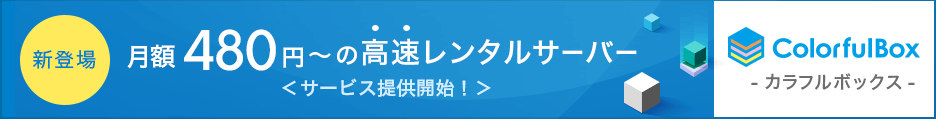|
昼下がりの駅構内はラッシュ時とまた少し違った喧噪に包まれていた。
午後の予定を同僚と相談しているサラリーマン、華やかな服に身を包み大きな荷物を片手に談笑している女性の一団、あるいは携帯電話を開きながらも友人とのおしゃべりに余念のない学生たち。駅を中心にあらゆる人が集い楽しむ快適空間、というコンセプトで作られたエキナカを、北陸新幹線は歩いていた。
少し遅めの昼食にしようと足を運んだのはいいけれど、どうにも目移りしてしまう。立ち食い蕎麦屋しかなかった頃とは違い、和洋中と様々な店が軒を連ねているのだ。選択肢が多いのはいいことだけれど、さて、どうしたものか。昨日は中華にしたから今日はさっぱりとしているものの方がいいかな、等と悩みながら歩いていくと、少し離れたところの店先に女性客が何人か集まっているのが見えた。
エキナカに入っている店舗は乗り換え客の動線を丹念にリサーチして配置されている。そして外観が洒落ているところが多い。その相乗効果だろう、男性客だけではなく女性の利用客も結構多いらしい。駅がにぎやかになるのは、路線としてとても嬉しいことだ。
それにしても、と何かを熱心に見ている様子を遠く眺める。女性客が集まっているということは、洋菓子でも扱っている店だろうか。ショーケースに並べられた色とりどりのケーキ。それを見つめる女性のきらきらとした眼差しを思い浮かべて、なんだか微笑ましいような気持ちになった。
かく言う北陸も甘いものは結構好きな方なので、彼女たちの視線の先にあるものが気になっていた。けれど今優先しなければならないのは昼食である。また後で見に来ればいいか、ときびすを返そうとして、その足が止まった。
見覚えのある緑の制服が、女性客の向こう側にちらりと見えたのだ。
「上越先輩…?」
襟足や頬に軽くかかる少し長めの直毛をさらりと揺らし、両手はポケットに突っ込んだまま、女性客の頭ひとつ分よりも上から店先をのぞき込んでいる。その横顔は間違いようもなく、上越新幹線その人だった。
甘いものより遙かに辛いものの方を好む上越がこんな店に来ているなんて珍しい。自分で食べるため、ではないだろう。それならきっと、誰かのために。
「東北先輩にでも…買っていくんだろうな」
北陸の頭の中にぱっと浮かんだのは、JR東日本のお父さん(と上越先輩が言っていた)、東北新幹線の顔だった。双子新幹線の片割れ。上越が誰よりも何よりも一番に気にかける存在。
上越に対する想いの強さなら、北陸は誰にも負けない自信がある。けれど。
「あっれ、北陸じゃない。こんなとこでどうしたの?」
唇を噛み手を強く握り締めたところで、後ろから不意に声を掛けられた。驚いて振り向く。そこには、にこやかな笑顔を浮かべた秋田新幹線がいた。
「秋田…先輩、こそ。どうしてここに」
「うん、僕? 僕は、ここのエキナカでチョコレートフェアをやってるって聞いたから、―――ああ、北陸も見に来たんだね。それじゃ一緒に行こうよ!」
「え、あの、僕はちが…っ!」
肩を叩かれ腕を掴まれて引きずられるように連れていかれる。この先には上越先輩が、と焦って見遣ったけれど、その姿はもうどこにも見えなかった。
そもそも焦るようなことは何もないのだ。運行に支障のない範囲であれば、休憩時間などに関してはある程度の裁量が与えられている。食事のついでに洋菓子店へ寄ってちょっとした菓子を買って帰るくらい、何ということもない。それが自分のためだろうが誰かのためだろうが、菓子を買うという行為に違いはないのだ。
見てはいけないものを見てしまったような気になっていたのは、北陸の一方的な思い過ごしだ。それでも鉢合わせしなくてよかった、とどこかほっとしながら、北陸は秋田と一緒に店先のショーケースをのぞき込んだ。
「もうすぐバレンタインだからね。こういう時じゃないと買えないチョコとか、ちゃんと買って食べておかないと」
「え、―――ああ、そういえば」
秋田に言われてようやく気付く。だから女性がこんなに集まっていたのか。今年ももうそんな時期になっていたんだな、と、業務に忙殺されてすっかり忘れていた自分に内心苦笑した。
「自分用のチョコ、どれにしようか毎年迷うんだよねぇ。―――あ、今年もみんなにチョコあげようと思ってるんだ。楽しみにしてて!」
「本当ですか? ありがとうございます。秋田先輩が選んでくださったチョコはどれも本当においしいので、今年も楽しみにしてます」
北陸の言葉に満面の笑みで秋田が大きく頷いた。それに笑顔を返して、北陸は再度ショーケースへと視線を向けた。
長野新幹線と呼ばれていた頃から毎年欠かさず、北陸は上越にバレンタインのチョコレートを贈っている。お返しを期待しているわけではないのだけれど、上越はホワイトデーに北陸へお返しを買ってきてくれる。それが例え義理だとしても、それを買う瞬間は北陸のことを少しでも考えてくれているのだと思うと、とても嬉しい。
けれど、上越からバレンタインにチョコレートを貰ったことはない。もちろん、上越がバレンタインのチョコレートを誰かにあげているかどうか、なんてことも知らない。
さっき見かけたのはやっぱり、誰かにあげるためだろうか。そうかもしれない、と思うと、少しだけ胸が痛んだ。
「僕に、…だったらいいのに」
それはあり得ない。そんな確信があった。
「ん、北陸? 何か言った?」
「いえ、何でもないです。―――そうだ、秋田先輩、甘いものが苦手な人でも喜んでくれそうなチョコレートってありませんか?」
「んー、そうだねぇ」
カゴいっぱいにチョコレートの箱を入れた秋田が、思案気に首を傾ける。
北陸になってから気付いたことなのだけれど、上越は甘いものがそれほど好きではないらしい。長野だった時は上越に贈ったチョコレートを毎年二人で一緒に食べていたので気付かなかったのだ。
「柿の種にチョコレートかけてるやつは? 甘いのとしょっぱいのが同時に味わえて、僕は結構好きだけど」
「…そういうのじゃないのは、ないでしょうか…」
以前『これなら!』と思い贈ってみたら、大不評を食らったのだ。『甘いのか辛いのか、どっちかにして欲しいよね』とため息をついた横顔にへこんだことを思い出す。大好きだと思うこの気持ちを籠めて贈るのだ。できることなら本当に喜んで貰いたい。
「―――うん、こないだ貰った情報誌でそんなチョコの特集してた気がする。後で見せてあげるから、時間ができたらおいでよ」
「ありがとうございます、それじゃ、後で伺いますね」
ぺこりと頭を下げてその場を離れる。まだ日数はあるから、秋田が話してくれた情報誌を見てから決めよう。そう考えながら北陸は、当初の目的だったお昼ご飯を食べにイートインのエリアへと向かうことにした。
つづく
|